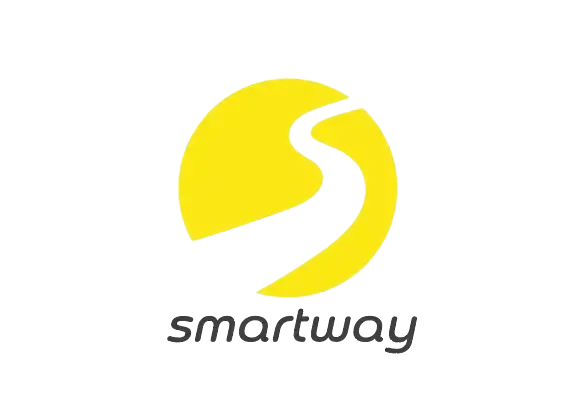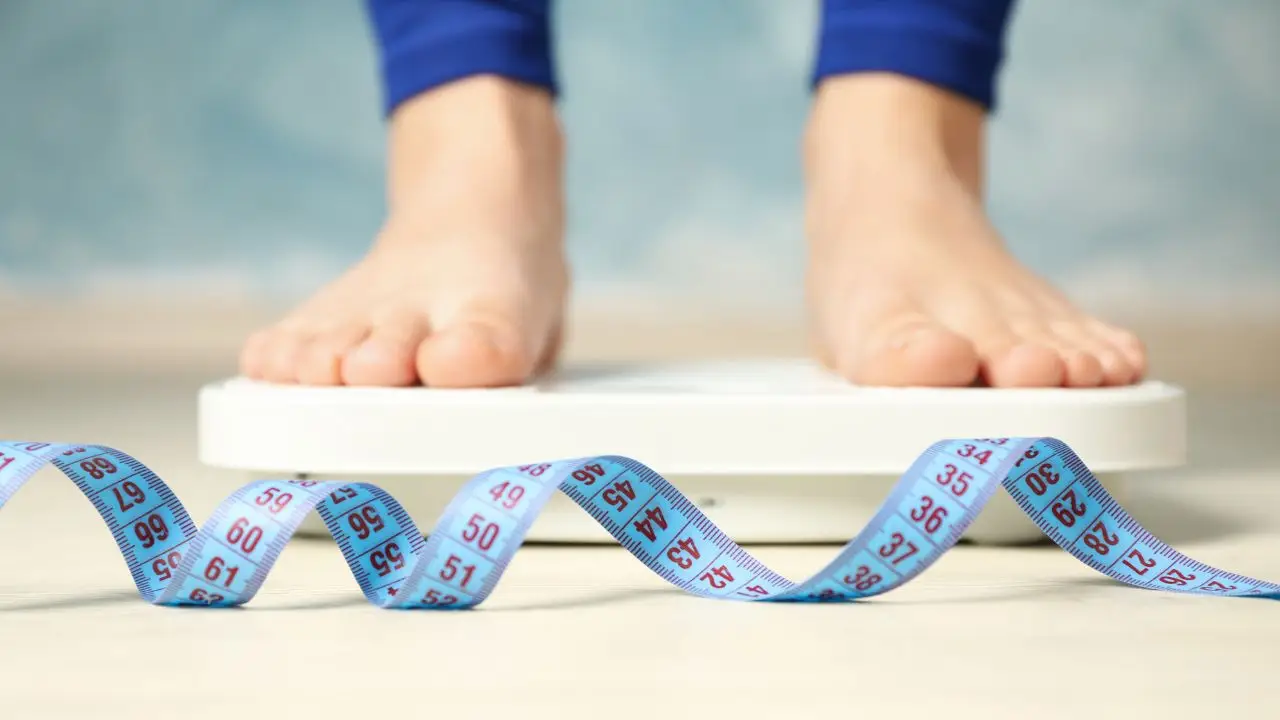運動を始めたのに体重が増えた!? その理由と正しい見方

こんにちは。いつもコラムをお読みいただきありがとうございます。
皆さんは「ダイエットのために運動を始めたのに、体重が増えてしまった…」
そんな経験はありませんか?多くの人が運動を始めた初期段階で、期待していた体重減少とは逆に数字が増えることに戸惑い、不安を感じます。しかし、それは決して運動の効果が出ていないという意味ではありません。むしろ、体が確実に変化している証ともいえるのです!
このコラムでは、運動を始めると体重が増える主な理由を身体の仕組みや運動生理学の観点からわかりやすく解説し、「体重」だけにとらわれない健康的な考え方をご紹介します。
筋肉が増えて体重が増える
最もよくある理由の一つが、筋肉量の増加です。
運動、特に筋力トレーニングやHIIT(高強度インターバルトレーニング)を行うことで、筋繊維が刺激され、修復と成長が起こります。この過程で筋肉が発達し、結果として体重が増えることがあります。
筋肉は脂肪よりも密度が高いため、同じ体積でも重くなります。つまり、見た目が引き締まってスリムになっていても、体重は増加しているということも起こり得るのです。体脂肪が減って筋肉が増えた結果、見た目には大きな変化があるのに、体重計だけを見ると「増えた」と勘違いしてしまうというわけです。
水分の貯留とグリコーゲンの関係
筋トレや有酸素運動を行うと、筋肉はエネルギーとして「グリコーゲン」を使います。このグリコーゲンは、筋肉内に水分と一緒に蓄えられます。具体的には、1gのグリコーゲンに対して約3gの水分が結合します。
運動を始めると、体はエネルギー供給の準備のためにグリコーゲンの蓄積量を増やします。これによって一時的に体内の水分量が増加し、体重として現れることがあるのです。これはあくまで一時的なものであり、健康上問題のない自然な生理反応です。
筋肉の修復に伴う炎症反応
筋肉を使うと、筋繊維には微細な損傷が生じます。これに対して体は炎症反応を起こし、修復を進めます。炎症と聞くとネガティブな印象を受けるかもしれませんが、これは筋肉を強くするために必要なプロセスです。
炎症が起こると、その部位に血流や水分が集まり、一時的にむくみや体重増加が見られることがあります。特に運動を始めたばかりの頃は体が慣れていないため、この反応が顕著に出やすい傾向があります。
ホルモンバランスの変化
運動によって体内のホルモンバランスも変化します。たとえば、コルチゾール(ストレスホルモン)は運動中やその直後に一時的に上昇することがあります。コルチゾールには水分を体に保持しやすくする働きがあり、これも体重増加の一因となります。
また、女性の場合は月経周期の影響も無視できません。月経前はホルモンの変動により水分を溜め込みやすくなり、一時的に体重が増えることもあります。運動との相互作用で変動が大きくなることもあるため、女性は特に長期的な視点で経過を観察することが大切です。
体重より「体組成」に注目を
ここまでの話からわかるように、体重の増加=太った、とは限りません。むしろ、筋肉が増えたことで代謝が上がり、脂肪が燃焼しやすい体に変わっている可能性の方が高いのです。
そこで注目すべきは「体重」ではなく「体組成」です。体組成とは、体を構成する筋肉、脂肪、水分、骨などの割合を示すもので、最近では家庭用の体組成計でも簡単に測ることができます。運動を継続することで、筋肉量が増えて体脂肪率が減っていくと、たとえ体重に大きな変化がなくても確実に健康的な体に近づいています。
継続こそがカギ
運動の効果はすぐに現れるものではありません。特に筋肉の成長や代謝の変化は時間がかかるものです。だからこそ、体重という一つの数字だけに振り回されず、自分の体の変化を長い目で見てあげてください。
ウェアのサイズが緩くなった、階段を上っても息切れしなくなった、肩こりや腰痛が軽減した——そんな変化こそ、運動が体にもたらしてくれる本当の成果です。
ぜひ参考にしてみてくださいね!